| Q417★ボルタ電池に関する質問です。(1)酸化剤と還元剤を隔離して、導線でつなぐと電子の移動が起こり、これが電池のメカニズムだと習いました。一方で、ボルタ電池は反応するのは銅板ではなく、水溶液中の水素イオンとなっています。このような複雑な電池がはじめに発明されたのは、亜鉛が出した電子が銅板が受け取ると思って電池を作ってみたものの、あとで詳細な反応がわかるにつれて、電子を受け取っていたのが水素イオンだと判明した、ということなのでしょうか? (2)イオン化傾向が仮に強かったとしても、亜鉛の電子は亜鉛の原子核から引っ張られているはずで、何の外力もなしに、亜鉛がイオン化するはずはないと思いました。そこで、亜鉛板の近くにある水素イオンから電子を引っ張られて、亜鉛が亜鉛イオンに、水素イオンが水素になるなら、理解はできます。ただ、教科書などでは、イオン化傾向が強い亜鉛が、相手もいないのに勝手に電子を放出し、あまった電子が亜鉛板から銅板に移動すると書かれています。相手がいないのに、勝手に亜鉛から電子が出ていくということはありうるのでしょうか?また、もしその相手が銅板付近の水素イオンというのであれば、距離的に離れすぎているので、違和感があります。 (3) (2)と関連するのですが、亜鉛はなぜ近くの水素イオンと反応せずに、わざわざ銅板まで移動して水素イオンと反応する必要があるのでしょうか? ご質問をありがとうございます。 説明の一部に高校化学の範疇を越える内容を含みますので、よければ、末の参考文献、図書などを時間のある時にご自身でも勉強してみてください。また、直接、お会いして話していないので憶測にはなりますが、ご記載いただいた文面を見る限り何か誤解が誤解を生んでいるような気も致しますので、くどいようですが順を追って説明させていただければと思います。 (1)の返答 まず、大まかな認識としてはあっていると思いますが、正確には異なるかと思います。ボルタが初めて電池を発明したのは1800年のことで、その当時はまだ電子というものがどういうものかよくわかっていなかった時代になります。そもそも、ボルタの電池発明に至る着想に大きく貢献したのは、同じくイタリアの解剖学者ガルバーニの実験結果(カエルの足の筋肉が金属に触れて痙攣する)があったとされています。また、逸話として、このガルバーニの実験結果に興味を持ったボルタは自身の舌を金属板で挟んで苦味?を感じ(マネしないでくださいね)、金属が何か重要な役割をしている、と感じたとされています。そんなボルタは、当時、手に入れることができた様々な金属種の板の何通りもの組み合わせを試し(最終的には銅板と亜鉛板の組み合わせを選び)、そしてそれらの金属板の間を食塩などの水溶液を染み込ませた布で挟んでそれを何層にも重ねたもの(Voltaic Pileと呼ばれる)を作り、電流を初めて連続的に取り出すことに成功した(電池の発明)とされています。*補足ですが、このボルタの(大)発明は、その後の化学の発展への寄与が多大であり、ボルタの発明後、同年すぐにVoltaic Pileを用いカーライル・ニコルソンにより水の電気分解に成功し、「水素」と「酸素」の発生を確認している。さらにデイビーはさまざまな金属溶融塩を電気分解し、カリウム、ナトリウム、バリウム、ストロンチウム、カルシウム、マグネシウムなどの金属を初めて得ている。そしてデイビーの弟子にあたるファラデーは1833年、電気分解で生成する物質の量が、流れた電気量に比例するという「電気分解の法則」を発見した。さらに、現在、使用する化学用語「電気分解(電解)」「電極」「陽極」「陰極」「イオン」「陽イオン」「陰イオン」「電解質」などを作ったのもファラデーである。その数年後、ダニエルは、ボルタ電池をもとにさらに課題点を改良した通称「ダニエル電池」を開発した。1897年、トムソンが高電圧をかけた陰極から発生するものが原子よりも約1000分の1程度の質量の負電荷を持つ「電子」であることを発見し(電子の発見)、その後の1900年初頭に電子の振る舞いを記述する「量子力学」が主にシュレーディンガーの波動力学とハイゼンベルグ、ボルンらの行列力学と組み合わせて誕生することになる。ここで、ボルタ電池発明当初から確認されていた水の電気分解により発生する「水素」の生成機構(水素電極反応)についても、ボルタ電池が発明されてから約100年が経って、やっと電子の存在やその振る舞いについて明らかになった後、詳細に研究できるようになりました(1,2)。(2)の返答 イオン化傾向が仮に強かったとしても、亜鉛の電子は亜鉛の原子核から引っ張られているはずで、何の外力もなしに、亜鉛がイオン化するはずはないと思いました。 その通りです。亜鉛は、何も外力がかからなければ(例えば、極低温かつ遮光下で真空中とか)、イオン化しません。 そこで、亜鉛板の近くにある水素イオンから電子を引っ張られて、亜鉛が亜鉛イオンに、水素イオンが水素になるなら、理解はできます。 これも理解としては正しいです。亜鉛と水素のイオン化傾向(=酸化還元電位(標準電極電位ともいいます))を比べても、亜鉛の方が大きいので、亜鉛板電極に近づいた水素イオンがいれば自発的に亜鉛(0)から水素イオンへ電子が移り、結果、水素発生が起きます。ただ、この「自発的に電極から水素イオンに電子が移り、結果、水素が発生する」一連の化学反応の効率が、亜鉛と銅で比べたときに1000倍以上、銅の方が効率良く(速く)進みます。この銅の方が速く進むことについてよく「触媒的に」とか「触媒作用として」と表現します。その言葉の意味(由来)は、化学反応進行における障壁となる活性化エネルギーを下げ、より反応を速く進ませる効果のある物質を「触媒」と呼ぶことからきています。亜鉛より銅の方がなぜ速く進むかについては、1900年初頭から初まる「水素電極反応」(電極からの電子で水素イオンを還元し、水素発生させる)の研究からの流れで様々な金属電極で調べられており(詳細は専門的すぎるため割愛しますが)水素イオンと電極との間の電子移動効率の指標でもある「交換電流密度」の値が亜鉛と銅で1000倍以上異なるからです(銅の方が1000倍大きい)(5-8)。その値が大きければ過電圧も小さくなり基本的には電極反応速度も速くなります。 ここで再度、電極と直接繋がっている導線(素材は銅で、何不自由なく電子を移動できる電子伝導体)についても合わせて考慮すると、水溶液中で自由に動き回っている水素イオンに対して亜鉛板電極から直接電子が移る効率よりも、はるかに速く(効率良く)銅板電極上でその反応が起こると考える方が自然に感じるかと思います。とは言うものの、ボルタ電池の装置構成上、亜鉛板電極の方でも多少なりとも水素発生は起こってしまうようで、その課題を克服しているがダニエル電池でもあります。 ちなみに余談ですが、ボルタ電池の極めて単純な装置構成から、最近、よく中高生の夏休み課題の一つとして「レモン電池キット」というのが1,000円程度で市販されていると思います。このキットはまさにボルタ電池そのもので、身の回りの家庭でも体験できる手軽な電池ですので、もし興味があれば調べてみてください。*ただし、レモン一個程度では電圧も低く、(何層にも積み重ねたVoltaic Pileのように)4~5個を直列で繋ぐことで電圧(電子を動かそうする力に相当します)を稼がないと電球を光らせたりできないみたいです。ただ、教科書などでは、イオン化傾向が強い亜鉛が、相手もいないのに勝手に電子を放出し、あまった電子が亜鉛板から銅板に移動すると書かれています。相手がいないのに、勝手に亜鉛から電子が出ていくということはありうるのでしょうか? その通りです。あり得ません。電子の移動を伴う酸化反応と還元反応は必ずセット(ペア)で起きています。相手がいないとか、どちらか一方の反応だけ、とかは絶対に起きません。それは、電子というものが、何もないところに浮かんで存在することはできず、必ず、軌道と呼ばれる原子核からの束縛を受けながら回る軌道のようなものにしか存在できないことからきています。なので、 例えば、導線を伝わって移動する時も何らかの原子核からの束縛を受けながら 移動しています。また、もしその相手が銅板付近の水素イオンというのであれば、距離的に離れすぎているので、違和感があります。 上述の返答に記載の通り、導電性の高い導線素材で直接、電極間を繋ぐこと、また、交換電流密度の大きい銅板を使用していることにより、たとえ亜鉛板から移動してくる電子だとしても銅板付近での水素イオンに効率良く電子移動できている、ということになります。(3)の回答 これもすでに上に返答済みですが、この「わざわざ銅板まで移動して水素イオンと反応する」からこそ電池として機能しています。<参考文献> 1、「トコトンやさしい 電気化学の本 新飯」 / 石原顕光 日刊工業新聞社、2023年、ISBN 978-4-526-08274-0 2、「電池がわかる 電気化学入門」 / 渡辺正・片山靖 オーム社、2011年、ISBN 978-4-274-21053-2 3、「高校化学の教え方 -暗記型から思考型へ-」 / 日本化学会 編 丸善、1997年、ISBN 4-621-04274-2 --以下は大学で使われるレベルの本や文献ですので参考程度にとどめてください-- 4、電気化学 基礎と応用 / K. B. Oldham et. al. (大阪武男ら 訳) 東京化学同人、2015年、ISBN 978-4-8079-0847-9 5、H. Kita., J. Electrochem. Soc., 113, 1095 (1966). 6、喜多英明、日本化学雑誌、92, 99 (1971). 7、J. Tafel, Z. Physik. Chem., 50, 641, 713 (1905). 8、J. Horiuti and M. Polanyi, Acta Physicochim. USSR, 2, 505 (1935). 高2 (MN) 2024/07/05 |
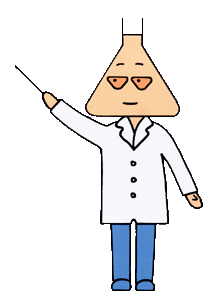 |