| Q426★(1)金属イオンの硫化物イオンとの沈澱について 硫化物イオンと金属イオンの沈澱のしやすさについて、イオン化傾向で説明している本が多いですが、このふたつにはどのような関係があるのでしょうか。 例えば、イオン化傾向の大きいカルシウムイオンは沈澱を形成せず、銅イオンは沈殿を生じるなどです。 なんとなく類似性はわかるのですが、よく考えると銅イオンは水和されていても、沈澱になっても銅イオンのままですし、これが単体→陽イオンのなりやすさとなぜ結びつくのか、わからなくなりました。 ネットで調べてみると、イオン化傾向は、エンタルピー的には、昇華熱 イオン化エネルギー 水和熱の合計で考えられるので、このイオン化エネルギーがイオン化傾向と関係しそうだなとは思ったのですが、それ以上はわかりませんでした。教えていただけると助かります。 (2)沈澱形成とイオン価について 以前の質問で、沈澱のしやすさは、イオン価の大きさと粒の大きさで説明しやすいとありました。 例えば、塩化物イオンと沈澱形成しやすいものとして、銀イオン、鉛イオンなどが教科書に書かれていますが、 ・なぜ電荷が大きい2族や13族の金属が含まれず、鉛イオンが沈殿しやすいのでしょうか ・なぜ鉄イオンのように三価のイオンを取れるものが沈澱せず、一価の銀イオンが沈澱するのでしょうか。 (3)酸化鉄や酸化銅の酸化数ついて 酸化鉄や酸化銅は複数の酸化数をとりますが、日常でよく見かけられるのはどの酸化数なのでしょうか。またそれはなぜでしょうか? (1)金属イオンの硫化物イオンとの沈澱について 【回答1】 イオン化傾向の大きな原子はイオン化して、陽イオンになりやすい性質があります。 陽イオンになれば、水分子の酸素が負電荷をもっているので、それと相互作用します。 つまりこれは、水分子が水分子とつながるよりも、陽イオンと相互作用するほうがエネルギー的に有利となり、その結果、水に溶けることになります。 言い換えると、水に溶けるというのは、その原子のまわりにどれだけ水分子が相互作用して囲んでくれるか、ということですので、イオン化しにくい原子は静電相互作用を水分子と作れないので、沈殿することになります。 例にあげられているカルシウムはイオン化傾向が大きいので、水に溶けやすく銅は水素よりもイオン化傾向が小さいので水に溶けにくく沈殿します。 単体の溶解(イオン化+水和)と化合物の溶解(水和)は、それぞれ、元の固体の安定度(格子エンタルピーやイオン化エンタルピー)とイオンの水和エンタルピーを総合的に決まるものといえます。 (2)沈澱形成とイオン価について ・なぜ電荷が大きい2族や13族の金属が含まれず、鉛イオンが沈殿しやすいのでしょうか【回答2】 【回答1】の答えにもありますが、イオン化傾向が大きな原子の場合、水分子と相互作用しやすくイオンとして水中に存在します。 そのため塩化物イオンと沈殿形成はしないです。 鉛イオンが塩をつくって沈殿形成しやすいのは、鉛イオンのイオン化傾向が小さいので塩化物イオンと鉛イオンがイオン結合して塩をつくり、この塩が水に溶けにくいからです。 この塩は電気陰性度が比較的大きなものどうし(Pb:2.33、Cl:3.16)のため、分子内の電荷の偏りが小さく電荷の偏りの大きな水において水どうしの相互作用をたちきって、この塩と相互作用させることが難しいため、水に溶けにくいです。 (1)の質問と同様に水和エンタルピーと格子エンタルピーの両方を考える必要があります。質問者が言うように静電的な効果は2族や13族のイオン(例えば、Ca2+、Al3+)は静電的な効果の観点ではイオン結合の観点から有利と思われます。一方、多価カチオンのイオン半径は小さくなるので、Cl-と結晶格子を作るのに不利となってきます。加えて、AgClやPbCl2ではイオン結晶といってもかなり共有結合性が出てくるため、それも安定な結晶格子形成の要因の一つになると考えられます。結果的に電荷の小さいAg+のほうが難溶性塩となると考えられます。 (2)沈澱形成とイオン価について ・なぜ鉄イオンのように三価のイオンを取れるものが沈澱せず、一価の銀イオンが沈澱するのでしょうか。【回答3】 イオン価数と関連はないです。すべてを説明することは難しいですが【回答2】の回答と同様かと思います。 (3)酸化鉄や酸化銅の酸化数ついて【回答4】 遷移金属イオンは原子に含まれる価電子を多数保持することができる軌道(d軌道)を持つため、様々な電子状態が生じえます。 安定な酸化数は電子配置と関係します。鉄は2+と3+が安定酸化数になるのは、原子状態の電子配置からエネルギーの高い4s電子が2つ抜けた2価状態(Fe2+)と、3d軌道からさらに電子が1つ抜けた3価の状態(d電子を5つ持つ電子配置)が安定になります。銅は、価電子を11個含む原子です。2個抜けた2価は安定ですが、d軌道がすべて電子で埋まった1価の酸化数(Cu+)も安定となります。 物質の安定性を考える上では、その電子構造を考えることが重要です。 高2 (KT) 2025/2/18 |
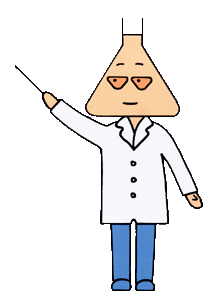 |