| Q438★高校で習う原子モデル・分子モデルが間違いであるということが気になり、調べてみたところ、軌道性結合と反結合性結合という言葉が出てきました。 電子が波動関数という状態で表され、通常の波と同様に、同位相同士の電子は強め合い、逆位相同士の電子は弱め合うということも、何となくわかりました。また、強め合った結果、電子の存在確率が上昇し、原子間の負密度が上昇することで、原子と原子を繋ぐ接着剤の役割をすることもなんとなくわかりました。 ただ、 ①軌道性結合と反軌道性結合が同時に発生するという意味がよくわかりませんでした。それぞれの電子が同位相同士であれば軌道性になるはずですし、逆位相であれば反軌道性になると思うのですが、これらが同時に発生するということは、重なり合う電子が同位相であり逆位相でもあるという、よくわからない状態になると思うのですが、これはどう理解したらいいでしょうか。 ②重なり合う電子の数が少なければ、より安定な軌道性結合に使われ、多ければ反軌道性結合に使われるとあったのですが、なぜ安定な軌道性結合だけなく、わざわざ不安定な反軌道性結合にも使われるのでしょうか? ①は、2つの原子軌道から、なぜ結合性軌道と反結合性軌道という2つの分子軌道ができるのか?という質問ですね。答えだけをいうと、『重ね合わせに使った原子軌道と同じ数だけ、分子軌道ができる』ことが必要で、そのためには2つの原子軌道を同位相で重ねる場合と、逆位相で重ねる場合の2つの分子軌道が生成されます。 このような波動関数の重なりを考える場合には、中学生までの単純な足し算のようなイメージではなく、大学で学習する行列の考え方が必要ですので、現時点でスッキリと理解できるような説明は難しいです。 ②の質問ですが、『ひとつの軌道には2つまでしか電子が入ることができない』というのが理由です。 水素分子だと電子は2つなので、2つの電子がともに結合性軌道を占有します。 しかしもし仮にHe2分子を想定すると、電子が4つあるので、結合性軌道だけでは足りなくなって、反結合性軌道にも電子が入ることになり、結果としてHe2分子は不安定になり存在できないことになります。 高2(KA) 2025/10/31 |
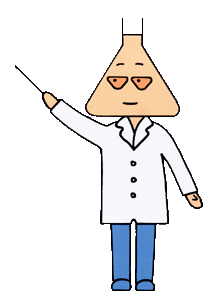 |