| Q420★ダニエル電池の仕切りを外した場合に電池としては機能しないが、原理的には電流が流れると思いずっと調べています。Q332の回答を読みました。Q15では原理的に流れるが効率良く取り出せないと書かれています。NHKforschoolの実験動画でも2日間通電しているダニエル電池の両極側のイオン濃度を測ると亜鉛負極側に銅イオンが0.1mol/L存在するにも関わらずプロペラは回っていました。亜鉛板と銅板を予め繋いでから溶液に浸けた場合(先に水溶液に浸けたモノを後から接続するのでは無く)に本当に電流計の針は全く振れないのでしょうか? 仕切り板を取り外すと、銅イオンが亜鉛電極側に拡散するので、Q332の回答にあるように『亜鉛電極表面で銅が析出する自己放電現象が起こり、電極表面が銅で覆われますので、電池としては機能しなくなる』ことが理論から予想されます。 ただ、亜鉛板が銅で覆われることで、亜鉛が溶けることのできる亜鉛板の面積は小さくなることなどから、電流値は小さくなっていくと予想されます。 さらに亜鉛電極の表面が銅で完全に覆われた場合でも、負極側と正極側の電解質濃度が異なる場合、電解質濃度差による電解質濃淡電池として機能しますので、全く電流が流れないわけではありません(かなり小さいとは思いますが)。 したがって実際の実験では、仕切り板を外した場合には、電流は徐々に小さくなっていくがゼロにはならないことが多いと思います。実際の現象が理論通りに、亜鉛板が完全に銅で覆われることは起こりにくいからです。理論を証明したいようなときには、実験をかなり理想的な条件で行うことが多いと思います。でも研究者って、理論と実際の違いにこそ好奇心を動かされる人達なんですよね。 身の回りで電池を使った製品が増えたためか、自由研究などで電池に関するいろんな実験がなされるようになってきましたが、電池の実験をする上で理解しておいて欲しい点について説明しておきます。 電池で電流が流れる(プロペラが回る)のは、電池が電気を流すエネルギー(電圧と容量の積に等しい)をもっているためです。スマホやパソコンなどで電池の容量が表示されていますが、これは電池の電圧から見積もっており、電池の電圧が小さくなるほど容量メーターも減っていきます。では電池の電圧は、何故生じるのかというと、電池の+極と-極とで起こる反応が違うからです。この違いですが、ダニエル電池の銅と亜鉛のように、溶解・析出する金属が違う場合に電池の電圧は大きくなります。また、同じ金属でもイオンの濃度が違ってもやはり電池には電圧が生じるので電流が流れます(これを濃淡電池といいます)。 じつは電池が電圧をもっていても、つまり放電できるエネルギーがあるのに電流が流れない場合もあります。例えば、ダニエル電池の銅板と亜鉛板の間を、イオンを通さないプラスチックで仕切ると、電圧はあるのに電気は流れません。これは電池のもつ抵抗(これを内部抵抗といいます)が非常に大きくなってしまったからです。この電池の内部抵抗というのは電気の流しやすさの問題で、電池の電圧とは関係ありません。つまり電池から電流を取り出すには、電圧という電気を流すエネルギーをもっていること、電気の流れを邪魔しないように電池の内部抵抗が小さい必要があります。 したがって、電池の実験で実験条件を変えて、そのとき電気の流れやすさ調べる場合には、実験条件により電池の電圧が変化したのか?それとも電池の中の抵抗が変化したのか?を区別して考えるとわかりやすいと思います。 中3 (TA) 2025/10/22修正(2024/07/19) |
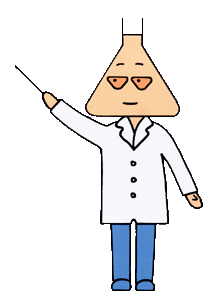 |